見る

智頭町
板井原集落(伝統的建造物群保存地区)板井原に向う道は、美しい杉木立に囲まれ、車一台通れるトンネルを越えると集落があります。 日本の山村集落の「原風景」を残し、昭和30年代にタイムスリップしたような気分が味わえる、昔の山村集落があります。
芦津渓谷の景観と水の流れと美しさを満喫させてくれるこの芦津渓谷は、春は新緑、秋は原生林の紅葉が全山を覆い、四季の自然が湖面に映えます。新緑・紅葉と見事な原生林が全山を覆い、その絶景は西日本屈指と評判が高く、ハイキング(中国遊歩道)、ヤマメ釣り、山菜料理(みたき園)も楽しめます。
2017年12月06日
智頭町の中心部から新見川沿いに県道を四キロほどさかのぼった新見地区の山中に豊乗寺(ぶじょうじ)はあります。創建は嘉祥年間(八四八ー八五一年)とされるが、戦国時代に兵火にかかり、現在の建物は徳川中期以降のものと伝えらています。
蒙古来襲の頃、弘安元年(1278)に信州の諏訪大社の分霊をいただき、古くから軍神や鎮火の守護神として崇敬されてきました。現在の本殿は天保3年(1832)、幣拝殿は明治37年(1904)に改築されました。また、諏訪神社の境内には欅の大木に混ざって多くの楓樹があり、その紅葉は壮観で、古くから紅葉の名勝地として地元に愛されています。
西粟倉村
駒の尾山(標高1,280m)は県下第2の高峰、自然の宝庫西粟倉の中でも豊富な高山植物が見られます。ダルガ峰林道登山口からは勾配も少なく【距離2km、標高差300m】子どもからお年寄りまで無理なく登ることが出来るうえ道中の眺望に優れており多くの駒ノ尾ファンが四季を通して訪れます。
ダルガ峰の山中にひっそりと佇む石柱群です。人為的に建てられたもの、と推測されていますが、確かな根拠は見つかっておらず、どうして建てたものなのかは謎のままです。付近では石器や弥生土器が発見されており、神秘的な古代の遺構です。
美作市
鎌坂峠(かまさかとうげ)入口から徒歩2分、武蔵神社手前にあるツツジ園。もともと棚田だった広さ約32aの敷地内に、約2000本約20種のツツジが植えられ、毎年4月中旬~5月中旬には美しい花を咲かせてくれる。
佐用町
戦国時代、織田軍・毛利軍の激しい戦いの地となった上月城の歴史を展示しています。また、明治の中頃から作られていた早瀬土人形の展示や、古くから作られていた和紙「皆田紙」の紙漉きの工程写真や、紙漉き道具などの展示をしています。
戦国時代の織田と毛利の攻防の地として、また尼子家再興に燃えた山中鹿之介の最後の地として知られる上月城。その起こりは延元元年(1336年)赤松氏の流れをくむ上月次郎景盛が太平山に砦を築き、後に二代目盛忠がこの地に本拠を移したことに始まります。
南北朝期に、赤松一族の別所敦範が利神山に山城を築いたのは貞和5年(1349年)、楠木正行が四条畷に戦死した翌年です。以来、赤松一族の拠点として約二百年を経て、慶長5年(1600年)関ヶ原の戦のあと、播磨52万石の領主池田輝政の甥、池田出羽守由之が平福領2万3千石の領主となりました。※落石等のおそれがあるため登城は控えていただいております。
江戸時代の町屋の代表的な建築様式を再現した資料館です。大屋根のけむり出し、くぐり戸のついたつりあげ大戸、葬式の際の出棺にだけ使う出口などの特徴があります。館内には、宿場を支えてきた商家の商い道具や民具類、利神城ゆかりの品々を展示しています。
法師塚がある山の斜面を利用した大規模なしゃくなげ園。日本しゃくなげと西洋しゃくなげ150種13,000本あまりが咲き誇ります。高山植物のしゃくなげが、標高わずか百メートル余の山の斜面に咲いています。
佐用町にそびえ立つ県指定天然記念物の大イチョウです。 これは赤松氏が全盛の頃にこの地にあった、如意輪山満願寺の境内に茂っていたイチョウで、いわば佐用の歴史の生き証人なのです。 台風で枝が折れ、幹を落雷で裂かれるなどの苦難にも耐てきたその威容は、佐用の象徴ともなっています。
大撫山山頂に広がる兵庫県立大学 西はりま天文台には、公開用としては世界最大の2mのなゆた望遠鏡を備えた天文台があります。天文台を中心に自然を生かした散策路やグループ・家族用ロッジの宿泊施設などの施設があります。
わずか30年で城下町としての用を終えた平福は、その後、江戸時代には因幡街道最大の宿場町として栄えました。城下町から宿場町へ。当時を物語る古文書、遺構・遺物など伝承されてきた歴史の断片が、町並みや生活品などに残っています。
上郡町
宝林寺境内に隣接し、「赤松三尊像」と呼ばれる赤松円心・円心の三男則祐・別法和尚(雪村友梅の説もあり)および則祐の娘千種姫の木坐像(それぞれ県指定文化財)をはじめ、円心や赤松家ゆかりの文化財を陳列しています。
2017年12月07日
上郡町郷土資料館は上郡町内の郷土資料を保存・公開し、小学生からお年寄りまで幅広い年齢層の人々に、郷土の歴史・民俗資料などの文化財を通して、町の文化や生活の歩みをさぐり、将来の上郡町がどうあるべきかを考えてもらうために、昭和50年、上郡町合併20周年を記念して設立されました。
冨満高原の山頂に位置し、行基菩薩によって創建された伝えられる寺院で、通称『ボタン寺』と呼ばれています。 4月下旬~5月上旬にかけて、100品種、1,000株のボタンが色とりどりに寺院内を染めます。
「かみごおりさくら園」は、平成11年度に、森林景観促進環境保全事業により整備されました。河津桜をはじめ10種類、約1,000本のみごとな桜が美しい花をつけ、毎年さくらまつりが開催されます。並木のあでやかさと香りで、やさしい春の日和をお楽しみください。
鳥取市
日本最大級の海岸砂丘。個性的な地形や見どころも多く、季節や時間帯によって様々な表情を見ることができる。夏の海に浮かぶイカ釣り漁の「漁火」や、クリスマスシーズンのイルミネーション「鳥取砂丘イリュージョン」も季節の風物詩。
岩美町
2019年02月21日
山陰海岸学習館は『山陰海岸ジオパーク』の魅力をさまざまな資料や映像で紹介しています。体験学習コーナーでは山陰海岸の砂や生きものを観察することができ、さまざまな学習相談にもご利用いただけます。
2019年02月21日
美しい浦富海岸を海から眺望できます。日本海特有の厳しい冬の気候によって形成された断崖絶壁、洞門や洞穴、そして白く輝く砂浜などに目を奪われます。船が島と暗礁の間をすり抜ける操縦も見どころの一つです。
八頭町
2011年01月06日
新興寺は平安時代から室町時代にかけて因幡国衙の役人の祈願所として栄え、因幡の国屈指の大寺でした。その境内にある宝篋印塔は「宝篋印陀羅尼経」を納めた供養塔であり、塔身の内側には月輪と梵字が刻まれています。至徳2年(1385年)の銘もみられ、南北朝時代の建造物とみられます。 県指定保護文化財。
2011年01月06日
澤神社についての伝承は不明ですが、江戸時代中期には獅子舞があったと伝えられている文献が残っています。獅子の胴体に使われている布(蚊帳)は鳥取藩主池田光仲から拝借した寝具で作ったと伝えられています。県指定無形民俗文化財。
2011年01月06日
白鳳時代、慈住寺という大加藍(だいがらん)が建てられ、南大門、三重塔、金堂、講堂などがあったとみられます。4月中旬、敷地内の八重桜が満開になり花見客が訪れます。国指定史跡。
2011年01月06日
青龍寺(せいりゅうじ)の宝物館に納められている立像。持国天は東方の守護神、また多聞天(毘沙門天)は、北方の守護神で災難よけの神です。いずれも鎌倉時代の寄木造りの極彩色で、高さが台座共に1メートルあります。国指定重要文化財。
2011年01月06日
17世紀初頭に建てられた、鳥取県内では最古の民家です。庭には樹齢およそ270年のヤブツバキがあり、白、赤、桃色の花を咲かせる珍しい「咲分け椿」が冬の矢部家住宅を一層引き立てています。国指定重要文化財。
2011年01月06日
和同2年(西暦709年)に行基(ぎょうき)が開いたといわれ、婆ケ城主の小松氏の祈願所でした。境内には後醍醐天皇のお手植えと伝えられる銀杏など、巨木が多く存在し、四季折々に美しい景観を見せています。鳥取県の指定天然記念物。
倉吉市
2019年02月21日
玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は江戸、明治期に建てられた建物が多く、今でも当時の面影を見ることができます。玉川に架けられた石橋や、赤瓦に白い漆喰壁の落ちついた風情のある街並みを歩くと、時間がゆっくり流れていくのが感じられます。
2019年02月21日
1605年に開創された曹洞宗の名刹。境内には、「南総里見八犬伝」のモデルとなった安房国(千葉県)館山城最後の城主、里見安房守忠義と8人の家臣が葬られてます。忠義は29歳の若さでこの世を去りましが、倉吉には8年間在住し、その折りに寄進したと伝えられる「古三彩鉢皿」が今も秘蔵されています。
2019年02月21日
1900年建築の主屋は切妻造り、棧瓦葺き、平入、木造2階建で、倉吉の伝統的な町屋形式を保持しています。また、主屋と渡り廊下で接続する離れは 1930年に建築され、造りは主屋と同じく、各所に上質の材を用い、昭和初期の熟達した和風の造詣を残しています。
2019年02月21日
打吹公園は山陰随一の桜の名所。春になると、多種多数のさくらやツツジが咲き、多くの観光客でにぎわいます。また、園内には博物館、動物宿舎のほか、すもう場、野球場、テニスコート、陸上競技場などの総合運動場もあります。
2011年01月06日
緑の彫刻プロムナード公園の一角にある記念館は、旧倉吉線「打吹駅」跡地に建てられています。館内には倉吉線に関する資料や写真パネルが展示してあります。また、記念館横には当時活躍したSL機関車が展示してあります。
2011年08月23日
倉吉市の保存林に囲まれた神社。御祭神は賀茂別雷神(かもわけいかづちのかみ)で、京都の上賀茂神社より勧請した神様。大自然を支配する神様で、災い除けにご利益があるとされている。
2011年08月22日
打吹公園内にある博物館は現代建築の粋を集めて設計されたものです。「倉吉博物館」には前田寛治・菅楯彦などの郷土ゆかりの作品、郷土の歴史・考古民俗資料などが展示されています。
湯梨浜町
2011年01月06日
湖面は鶴が翼を広げた形をしていることから別名「鶴の湖」と呼ばれ、しじみ・ワカサギ・シラウオ・コイ・フナなどが豊富です。特にエビ・ワカサギ・シラウオなどを獲る仕掛けの「四ツ手網」は、東郷湖の落ち着いたシンボルになっています。
三朝町
北栄町
2012年03月15日
コナンの里拠点施設として、作者の思い出の所蔵物や作品展示、「名探偵コナン」登場のターボエンジン付スケートボードなどアトラクションも設置するアミューズメント施設。
琴浦町
2011年01月07日
1819年蔚珍郡を就航した商船が嵐で難破し、赤碕沖に漂着した船長以下12名を手厚くもてなし、一行を無事本国へ生還させた。漂流地を見下ろせる丘に整備されている。
2011年01月07日
奈良前期・白鳳時代の法隆寺式伽藍配置の寺院跡で、寺域が東西160m・南北250mの約4万m2に及ぶ大規模なものです。出土遺物が優秀であることなどから、山陰で唯一の国の特別史跡に指定されています。
2011年01月07日
彫刻家・流政之先生作の三体の石像です。高さ4.33m、白御影石製。「昔の旅姿」を象徴し、見る人それぞれの胸に深い印象を与えています。菊港先東突堤に、北東の荒波に向かって立っています。
2011年01月07日
鎌倉末期の作で、安山岩製・高さ約3mの宝塔様式と宝篋様式の二様式を持つこの塔は、赤碕付近にしか見られないことから、赤碕塔と名付けられました。 花見潟墓地の一角にあります。
2011年01月07日
波音と潮風に包まれて、花見潟に静かに佇む無数の墓地群。一ヶ所の海岸に集中している墓地は、全国的にも珍しく西日本最大級のものです。夜は盆灯篭の灯が花見潟に映え、幻想絵巻をひもといたよう。
2011年01月07日
貞享5年(1688年)建築の民家。当初は落棟客間の変形6間取り、後に広間5間取りに復元されました。防火のため、竈(かまど)の天井に泥を塗るなど、随所に「暮らしの知恵」が施されています。
2011年01月07日
加勢蛇川上流の地獄谷にあり、落差42mを誇る二段の滝で、平成2年に「日本の滝百選」に選ばれた県下最大の名滝です。一向平から、遊歩道が整備されており、途中、大山滝不動明王の湧き水や、吊り橋を渡りながら、片道約30分のハイキングコースとして、大勢の観光客で賑わっています。
2011年01月07日
船上山万本桜公園で毎年4月29日(みどりの日)に開催。町内外1万人の人出で賑わいます。後醍醐天皇ゆかりの負上げ競争や、大宝探しなどの催しものと共に、遅咲きの八重桜を満喫できます。
2011年01月07日
春日神社にあり、樹齢は千年を越すと言われ、周囲が11.4m、高さ15mのスダジイの大木。標高が高くなると生育しにくくこれほどのシイは非常に珍しい。歴史深い樹木の宝庫・琴浦町でも随一といえる銘木で、平成元年に環境庁の調査でシイの木では巨木日本一に指定された。
兵庫県北部
2011年01月07日
寺伝によると慈覚大師の開基と伝えられ、醍醐天皇の皇子「空也上人」が仏門に入り念仏行者となって諸国行脚の末、天禄3年(972)この地で入定されたと伝えている。時の円融天皇が精舎を建立して転法輪寺と勅号されたという。
2019年03月01日
新余部橋りょうは、平成22年8月12日に供用開始されたPCエクストラドーズド橋です。旧余部橋りょうは、風速が秒速20m/sで列車運行が不可能でしたが、新余部橋りょうは、秒速30m/sまで列車運行が可能になりました。
兵庫県南部
2019年03月01日
築城以来400年、この地に砦が築かれてからでは600年を超える歴史があり、数多くの国宝、重要文化財、伝説などを有する、姫路市のシンボル。 法隆寺とともに1993年12月、日本で初めてユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界文化遺産に登録され、日本に現存する城の中でも世界的に高い評価を受けています。
2011年01月07日
世界文化遺産姫路城を借景に、姫路市制百周年を記念して造営された池泉回遊式の日本庭園。江戸時代の地割りを活かした9つの趣の異なった庭園群で構成されており、面積は約1万坪(3.5ha)もあります。
2019年03月01日
康保3年(966)性空上人(しょうくうしょうにん)によって開かれました。この山に登るものは菩提心をおこし、峰にすむものは六根を清められるという文殊菩薩のお告げがあり、摩尼殿上の白山で六根清浄の悟りを得たと伝えられています。



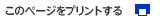




































































































鳥取県最大の宿場町として栄えた智頭宿には、藩政時代の街並みが残っております。日本庭園を有する「石谷家住宅」(国指定重要文化財)をはじめとする数々の見どころがあります。